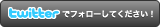このブログは生長の家の真理普及のために運営していますが、内容や発言はすべて私個人に責任があります。宗教法人「生長の家」の公式見解ではありませんので、予めご了承ください。 ご不明な点は、shingonsni@gmail.com までお問い合わせください。 (ブログ開設日:平成21年9月15日)
リンク
フリーエリア
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
先日、私が夕食をとるために、行きつけの定食屋に行ったときのことです。
店に入ると、初めて見かける店員さんが一人いました。
「新人さんが入ったんだな」と思いながら、案内された席に着きました。
私は注文をし、食事が出て来るのを待っていました。
私の背後から、以前から働いている店員さんが、新人の店員さんに、注文の聞き方や食事の運び方などを教えている声が聞こえてきました。
「注文を聞くときには、こう聞いて!」
「これをお客さんのところに持って行って、こう言って!」等々。
先輩の店員さんは、きっと自分が新人の時に先輩から教えられた通りにアドバイスしていたのだと思います。
私は、先輩店員と新人店員とのやり取りを、新鮮な気持ちで聞いていました。
しばらくすると、次のような台詞が聞こえてきました。
「お客さんは“みんな優しい人ばかり”だから、大丈夫だからね!」と。
おそらく、新人の店員さんは、つい先ほどから、現場の配置に付き始めたのでしょう。
先輩店員さんは、新人店員さんが不安そうにしていたのを気にして、このように言ったのかもしれません。
私は、先輩店員が発した“気の利いた台詞”を聞いて、「こういう言い方ってあるんだな!」と感心しました。
私は“みんな優しい人ばかり”という言葉に、「たしかに本来“みんな優しい人ばかり”だよな! 生長の家で言えば、ある意味、相手の実相(本当の姿)を観ている台詞と言えるよな!」と思いました。
私が食事を終わって、レジに行くと、新人の店員さんが引き続き応対してくれました。
私がレジの新人店員さんの胸元にふと目をやると、中国名(と思われる)の名札が付いていました。
新人の店員さんは、先輩店員さんから「レジではこうするの!」とか「この時にこう言うの!」等々、会計時のアドバイスをいろいろと受けながら、(覚束なくは見えましたが)レジを打っていました。
最近は日本でも、コンビニや外食産業等のさまざまな場所で働いている、アジア系の外国人(あるいは外国出身の方)の姿を数多く見かけます。
私がこういった外国(出身)の方々と接する際にいつも感じることは、「異国の地・日本に来て、おそらく大変なことや不安なこと等がいろいろとある中で、一所懸命に働いていて素晴らしいよな!」ということです。
人種や民族、国籍、宗教、出身地、言語等の違いを超えて、さまざまな人間同士が行き交い、触れ合う現代社会。
もしかすると、この先輩店員さんは人生で初めて、外国人(外国出身者)にいろいろと教えるという体験をしていたのかも知れません。
今回、先輩店員の“気の利いた台詞”に、国籍や出身地、宗教、使用言語等が違っても、人間として、相手を思いやる気持ちは共通なんだと、改めて感じた“一コマ”でした。
店に入ると、初めて見かける店員さんが一人いました。
「新人さんが入ったんだな」と思いながら、案内された席に着きました。
私は注文をし、食事が出て来るのを待っていました。
私の背後から、以前から働いている店員さんが、新人の店員さんに、注文の聞き方や食事の運び方などを教えている声が聞こえてきました。
「注文を聞くときには、こう聞いて!」
「これをお客さんのところに持って行って、こう言って!」等々。
先輩の店員さんは、きっと自分が新人の時に先輩から教えられた通りにアドバイスしていたのだと思います。
私は、先輩店員と新人店員とのやり取りを、新鮮な気持ちで聞いていました。
しばらくすると、次のような台詞が聞こえてきました。
「お客さんは“みんな優しい人ばかり”だから、大丈夫だからね!」と。
おそらく、新人の店員さんは、つい先ほどから、現場の配置に付き始めたのでしょう。
先輩店員さんは、新人店員さんが不安そうにしていたのを気にして、このように言ったのかもしれません。
私は、先輩店員が発した“気の利いた台詞”を聞いて、「こういう言い方ってあるんだな!」と感心しました。
私は“みんな優しい人ばかり”という言葉に、「たしかに本来“みんな優しい人ばかり”だよな! 生長の家で言えば、ある意味、相手の実相(本当の姿)を観ている台詞と言えるよな!」と思いました。
私が食事を終わって、レジに行くと、新人の店員さんが引き続き応対してくれました。
私がレジの新人店員さんの胸元にふと目をやると、中国名(と思われる)の名札が付いていました。
新人の店員さんは、先輩店員さんから「レジではこうするの!」とか「この時にこう言うの!」等々、会計時のアドバイスをいろいろと受けながら、(覚束なくは見えましたが)レジを打っていました。
最近は日本でも、コンビニや外食産業等のさまざまな場所で働いている、アジア系の外国人(あるいは外国出身の方)の姿を数多く見かけます。
私がこういった外国(出身)の方々と接する際にいつも感じることは、「異国の地・日本に来て、おそらく大変なことや不安なこと等がいろいろとある中で、一所懸命に働いていて素晴らしいよな!」ということです。
人種や民族、国籍、宗教、出身地、言語等の違いを超えて、さまざまな人間同士が行き交い、触れ合う現代社会。
もしかすると、この先輩店員さんは人生で初めて、外国人(外国出身者)にいろいろと教えるという体験をしていたのかも知れません。
今回、先輩店員の“気の利いた台詞”に、国籍や出身地、宗教、使用言語等が違っても、人間として、相手を思いやる気持ちは共通なんだと、改めて感じた“一コマ”でした。
PR
11月19日~22日までの4日間、長崎県の生長の家総本山(リンク先に秋季大祭の模様がアップされています)に出張で行ってきました。
この4日間で、いろいろと素晴らしい体験をさせていただきました。

まず初めに、私が滋賀県にいた時にお世話になったW坂さん(男性、76歳)と久しぶりにお会いすることができました。
W坂さんは今回、本部褒賞の受賞のため、総本山にお越しになっていました。
W坂さんは、以前より目が一段と悪くなられたようで、介添えを必要とされていましたが、非常にお元気そうでした。
現在もまだバリバリの“現役”で、滋賀教区の「湖国練成会(生長の家の合宿形式のつどい)」の練成主任(代行)として、活躍されています。
W坂さんは普段は非常に無口で温和しい方ですが、いったん講話をされたり、「笑いの練習」の先導をされると、“別人”のようになられる方です。
W坂さんは、「一体どこから、こんなに力強く、ハキハキとした声が出てくるんだろうか!」と思うくらいの声量で、生長の家の講師として人前で話される方です。

今回の式典のため、生長の家の真理の伝道と普及に長年に亘ってご尽力された方々が多数、日本全国をはじめ、世界各国からお越しになられ、本部褒賞を受賞されていました。
改めて、こういった方々のご貢献のお陰で、吾々生長の家の“今”があるんだと痛感します。

祭典の途中で、50代後半くらいのご夫婦が、体の不自由なお母さんを介添えしながらお越しになりました。
私は会場の外で「場内係」として応対しました。
お母さんは“手すり”を使っても、階段を昇ることはとても困難そうでしたので、車椅子にお乗りではなかったのですが、車椅子用の通路を通って、エレベータで会場に入ってもらうようにご案内しました。
私にとっては当然のことをしただけですが、式典が終わって、三人はわざわざ私に対して、非常に丁重に、お礼の言葉を何度もくださいました。
むしろ私にとっては、体の不自由なお母さんに寄り添い、体を抱きかかえるようにして支えながら一緒に歩かれる息子さんと、お義母さんの荷物や靴などを抱えて後ろから付いてこられるお嫁さんの真摯な姿に、こちらが温かい気持ちになりました。
「“親孝行”をされる息子さんご夫婦の姿って、本当に美しいな!」と私はこの時、心から感動しました。
お陰さまで、私自身も家族も普段からいたって健康ですので、なかなか体の不自由な方の気持ちや視点が分かりにくいというのが本当のところです。
しかし、今回、三人の姿を通して、階段の両脇にさりげなく設置されている“手すり”の大切さや、車椅子用のスロープやエレベーターの有り難さに改めて気づきました。
総本山で、本当に素晴らしい4日間を過ごさせていただけたと思います。
この4日間で、いろいろと素晴らしい体験をさせていただきました。
まず初めに、私が滋賀県にいた時にお世話になったW坂さん(男性、76歳)と久しぶりにお会いすることができました。
W坂さんは今回、本部褒賞の受賞のため、総本山にお越しになっていました。
W坂さんは、以前より目が一段と悪くなられたようで、介添えを必要とされていましたが、非常にお元気そうでした。
現在もまだバリバリの“現役”で、滋賀教区の「湖国練成会(生長の家の合宿形式のつどい)」の練成主任(代行)として、活躍されています。
W坂さんは普段は非常に無口で温和しい方ですが、いったん講話をされたり、「笑いの練習」の先導をされると、“別人”のようになられる方です。
W坂さんは、「一体どこから、こんなに力強く、ハキハキとした声が出てくるんだろうか!」と思うくらいの声量で、生長の家の講師として人前で話される方です。
今回の式典のため、生長の家の真理の伝道と普及に長年に亘ってご尽力された方々が多数、日本全国をはじめ、世界各国からお越しになられ、本部褒賞を受賞されていました。
改めて、こういった方々のご貢献のお陰で、吾々生長の家の“今”があるんだと痛感します。
祭典の途中で、50代後半くらいのご夫婦が、体の不自由なお母さんを介添えしながらお越しになりました。
私は会場の外で「場内係」として応対しました。
お母さんは“手すり”を使っても、階段を昇ることはとても困難そうでしたので、車椅子にお乗りではなかったのですが、車椅子用の通路を通って、エレベータで会場に入ってもらうようにご案内しました。
私にとっては当然のことをしただけですが、式典が終わって、三人はわざわざ私に対して、非常に丁重に、お礼の言葉を何度もくださいました。
むしろ私にとっては、体の不自由なお母さんに寄り添い、体を抱きかかえるようにして支えながら一緒に歩かれる息子さんと、お義母さんの荷物や靴などを抱えて後ろから付いてこられるお嫁さんの真摯な姿に、こちらが温かい気持ちになりました。
「“親孝行”をされる息子さんご夫婦の姿って、本当に美しいな!」と私はこの時、心から感動しました。
お陰さまで、私自身も家族も普段からいたって健康ですので、なかなか体の不自由な方の気持ちや視点が分かりにくいというのが本当のところです。
しかし、今回、三人の姿を通して、階段の両脇にさりげなく設置されている“手すり”の大切さや、車椅子用のスロープやエレベーターの有り難さに改めて気づきました。
総本山で、本当に素晴らしい4日間を過ごさせていただけたと思います。
アメリカのアマゾン社がキンドル端末から、電子メールを使って、知人・友人等に電子書籍をプレゼントできるサービスを開始しました。
このサービスの概要(流れ)を簡単に説明します。
(1)キンドル端末の所有者は、キンドル・ストアでプレゼントしたい電子書籍を購入して、 「Give as a Gift」 アイコンをクリックします。
(2)次に、プレゼントしたい相手の電子メールアドレスを指定します(もちろん「メッセージ」も送れます)。
(3)すると、相手のもとにプレゼントの通知メールが届きます。
(4)プレゼントされた相手は、このメールのリンクをクリックすれば、電子書籍をダウンロードできる、というものです。
なお、プレゼントされた電子書籍は、無料のキンドル・アプリを使えば、パソコンやアイパッド、アイポッドタッチ、アイホーン、アンドロイド、ブラックベリーなど、他の各種電子端末(アプリ)からも閲覧できるため、相手方はキンドル端末を持っていなくてもいいようです。
考えてみれば、他人へのプレゼント(贈呈)のための「機能」や「サービス」があるというのは、何か人間的で、素敵なことだと感じます。
キンドルのこのようなサービスを「どんな時に、誰を対象に使うだろうか?」と考えてみました。
「子どもや孫などの記念日(誕生日、入学進学、学校合格、成人・就職・結婚等の人生の節目など)に、本をプレゼントする」
「知人や友人、家族に、お薦めの本(自分が読んで感動したり、為になった本、是非読んで欲しい本など)をプレゼントする」、などなど。
いずれにしろ、相手のことを思ってプレゼントするわけです。
人間のこのような行為に、何か“ほのぼのした”気分になり、嬉しい気持ちになれます。
私は現在、紙媒体の書籍を購入する場合、おそらく5~7割方はアマゾンのサイトで購入していると思います。
利用されている方もいらっしゃると思いますが、実はアマゾンのサイトを見ると、同様のサービスを、紙媒体の書籍ですでに行っています。
私は普段は当然、購入した書籍の「送付先」を「自宅」にしますが、これまでに知人や友人、家族等に「是非読んで欲しいと思った本」をプレゼントするために、「送付先」を「相手方の住所」にして“贈呈”という形で送付したことが、何度かあります。
しかし考えてみれば、このように書籍等を誰かにプレゼント(贈呈)するということは、昔から行われてきたことに気がつきます。
私の家は、祖父母の代から「生長の家」を信仰していますが、私の父と母が結婚した時に、父方の祖母が、当時の神誌「生長の家」誌(現在の月刊誌)を、母宛に他の荷物と一緒に送付してくれたそうです。
(父と母からは、双方が「生長の家」を信仰していることは、結婚してから初めて知ったと聞いています。)
今は亡き祖母(平成8年に94歳の天寿を全う)は、「信仰している生長の家のみ教えを、息子の嫁に伝えたい」という思いから、私の母に神誌をプレゼントしたのだと思います。
「この神誌を読んで、嫁として、母として、女性としての天分等を学んで欲しい」という思いから、贈呈したのだと思います。
祖母の“このような思い”は、現在、私や私の姉妹にも伝わっているというわけです。
他人(ひと)に書籍等をプレゼントするのって、本当に素敵なことだと思います。
人間にはこのように、本来「自分以外の存在のことを心から考える」という、人間ならではの“本性”があるんだなと感じます。
話が大きく飛躍してしまいますが、各人が自分のことや自分の身内以外に、
(地球の人口:約70億人) -マイナス (自分と身内) ≒ (約70億人)
のことを常に考えて生きられるようになれば、どんなに素敵な社会になるだろうかと思います。
なお、アマゾンのサービスの詳細については、同社のこちらの頁をご覧ください。
(この記事は、アマゾンの当該サービスの利用促進を目的に書いたものではありません。)
このサービスの概要(流れ)を簡単に説明します。
(1)キンドル端末の所有者は、キンドル・ストアでプレゼントしたい電子書籍を購入して、 「Give as a Gift」 アイコンをクリックします。
(2)次に、プレゼントしたい相手の電子メールアドレスを指定します(もちろん「メッセージ」も送れます)。
(3)すると、相手のもとにプレゼントの通知メールが届きます。
(4)プレゼントされた相手は、このメールのリンクをクリックすれば、電子書籍をダウンロードできる、というものです。
なお、プレゼントされた電子書籍は、無料のキンドル・アプリを使えば、パソコンやアイパッド、アイポッドタッチ、アイホーン、アンドロイド、ブラックベリーなど、他の各種電子端末(アプリ)からも閲覧できるため、相手方はキンドル端末を持っていなくてもいいようです。
考えてみれば、他人へのプレゼント(贈呈)のための「機能」や「サービス」があるというのは、何か人間的で、素敵なことだと感じます。
キンドルのこのようなサービスを「どんな時に、誰を対象に使うだろうか?」と考えてみました。
「子どもや孫などの記念日(誕生日、入学進学、学校合格、成人・就職・結婚等の人生の節目など)に、本をプレゼントする」
「知人や友人、家族に、お薦めの本(自分が読んで感動したり、為になった本、是非読んで欲しい本など)をプレゼントする」、などなど。
いずれにしろ、相手のことを思ってプレゼントするわけです。
人間のこのような行為に、何か“ほのぼのした”気分になり、嬉しい気持ちになれます。
私は現在、紙媒体の書籍を購入する場合、おそらく5~7割方はアマゾンのサイトで購入していると思います。
利用されている方もいらっしゃると思いますが、実はアマゾンのサイトを見ると、同様のサービスを、紙媒体の書籍ですでに行っています。
私は普段は当然、購入した書籍の「送付先」を「自宅」にしますが、これまでに知人や友人、家族等に「是非読んで欲しいと思った本」をプレゼントするために、「送付先」を「相手方の住所」にして“贈呈”という形で送付したことが、何度かあります。
しかし考えてみれば、このように書籍等を誰かにプレゼント(贈呈)するということは、昔から行われてきたことに気がつきます。
私の家は、祖父母の代から「生長の家」を信仰していますが、私の父と母が結婚した時に、父方の祖母が、当時の神誌「生長の家」誌(現在の月刊誌)を、母宛に他の荷物と一緒に送付してくれたそうです。
(父と母からは、双方が「生長の家」を信仰していることは、結婚してから初めて知ったと聞いています。)
今は亡き祖母(平成8年に94歳の天寿を全う)は、「信仰している生長の家のみ教えを、息子の嫁に伝えたい」という思いから、私の母に神誌をプレゼントしたのだと思います。
「この神誌を読んで、嫁として、母として、女性としての天分等を学んで欲しい」という思いから、贈呈したのだと思います。
祖母の“このような思い”は、現在、私や私の姉妹にも伝わっているというわけです。
他人(ひと)に書籍等をプレゼントするのって、本当に素敵なことだと思います。
人間にはこのように、本来「自分以外の存在のことを心から考える」という、人間ならではの“本性”があるんだなと感じます。
話が大きく飛躍してしまいますが、各人が自分のことや自分の身内以外に、
(地球の人口:約70億人) -マイナス (自分と身内) ≒ (約70億人)
のことを常に考えて生きられるようになれば、どんなに素敵な社会になるだろうかと思います。
なお、アマゾンのサービスの詳細については、同社のこちらの頁をご覧ください。
(この記事は、アマゾンの当該サービスの利用促進を目的に書いたものではありません。)
先日、婚約を発表したイギリスのウィリアム王子とケイト・ミドルトンさん。
故ダイアナ妃の面影のあるウィリアム王子は、爽やかでかっこよく、イギリスの王族のお方らしく、さすが気品があるなと、以前から思っていました。
今回の報道で、28歳になられた王子を拝見すると、本物のイギリス・ジェントルマンらしい、風格漂わせる“大人な”男性になられたなと感じました。
ケイトさんは、貴族ご出身のダイアナ妃とは違って、“庶民”のご出身とのことですが、非常に美しく気品があり、知性的で、魅力溢れる、素敵な女性だと感じました。
ケイトさんは、ファッションセンスも抜群で、どんな格好をされても似合いそうな方です。
(私が言うのも何ですが、)イギリスの次々代の王になられる、王子のお后に本当に相応しい方だと感じました。
今回、お二人についての報道で特に感激し、感心したのが、ウィリアム王子が亡き母であるダイアナ妃の婚約指輪を、ケイトさんに送ったという話です。
日本の“庶民”出身の私の妹の話を出してきては大変失礼かもしれませんが、先日結婚した上の妹は、花婿のお母さんがご自分の結婚式で着られたという着物を、披露宴で着ていました。
確かに着物のデザインが少し古い感じはしましたが、私はこのことを知って、「(我が妹ながら)粋なことをするなあ!」 「“実の母親”にしろ、“魂の母親”(=配偶者の母親)にしろ、お母さんの着ていた着物を、花嫁が着るのって、何か素敵だな!」と感じました。
こういったことは“万国共通”なんだと思います。
故ダイアナ妃の面影のあるウィリアム王子は、爽やかでかっこよく、イギリスの王族のお方らしく、さすが気品があるなと、以前から思っていました。
今回の報道で、28歳になられた王子を拝見すると、本物のイギリス・ジェントルマンらしい、風格漂わせる“大人な”男性になられたなと感じました。
ケイトさんは、貴族ご出身のダイアナ妃とは違って、“庶民”のご出身とのことですが、非常に美しく気品があり、知性的で、魅力溢れる、素敵な女性だと感じました。
ケイトさんは、ファッションセンスも抜群で、どんな格好をされても似合いそうな方です。
(私が言うのも何ですが、)イギリスの次々代の王になられる、王子のお后に本当に相応しい方だと感じました。
今回、お二人についての報道で特に感激し、感心したのが、ウィリアム王子が亡き母であるダイアナ妃の婚約指輪を、ケイトさんに送ったという話です。
日本の“庶民”出身の私の妹の話を出してきては大変失礼かもしれませんが、先日結婚した上の妹は、花婿のお母さんがご自分の結婚式で着られたという着物を、披露宴で着ていました。
確かに着物のデザインが少し古い感じはしましたが、私はこのことを知って、「(我が妹ながら)粋なことをするなあ!」 「“実の母親”にしろ、“魂の母親”(=配偶者の母親)にしろ、お母さんの着ていた着物を、花嫁が着るのって、何か素敵だな!」と感じました。
こういったことは“万国共通”なんだと思います。
ウィリアム王子とケイトさんの婚約報道を受け、マスコミは、経済効果が○○億円になると予測されているとか、ケイトさん愛用のファッションブランドが来年は流行るだろうとか、報道しています。
こういった話はともかくとして、現在、失業率が高いイギリス社会が、お二人の結婚により「明るくなる」という話には、とても嬉しい気持ちになりました。
実は私は、大学3年生の夏休みにイギリスで一ヶ月ほどホームステイしたことがあり、日本と同じ島国で、伝統深い国であるイギリスは好きな国の一つなんです。
ウィリアム王子とケイトさん、お似合いのお二人の婚約(と結婚)に、遠く日本から、心からの祝福を送りたいと思います。
こういった話はともかくとして、現在、失業率が高いイギリス社会が、お二人の結婚により「明るくなる」という話には、とても嬉しい気持ちになりました。
実は私は、大学3年生の夏休みにイギリスで一ヶ月ほどホームステイしたことがあり、日本と同じ島国で、伝統深い国であるイギリスは好きな国の一つなんです。
ウィリアム王子とケイトさん、お似合いのお二人の婚約(と結婚)に、遠く日本から、心からの祝福を送りたいと思います。
10月20~21日に、旅行で群馬県に行きました。
この群馬旅行で久しぶりに「ある体験」をしました。
それは「芋掘り」です。
「芋掘り」と言えば、小学生の時に学校の農園で行って以来、ウン十年ぶりです。
考えてみれば、最近、私自身、日常生活の中で「土に触れる」ことがほとんどありません。
土などの自然由来のものに触れる機会を、日常的に失ってしまっているのが、都会に住む吾々現代人の生活なんだと感じます。

「芋掘り」で味わった、土の感触は何とも言えません。
土の中に手を突っ込んで、芋を掘り起こしているときに、腕から先の肌の感覚が鋭敏になり、活性化するのを感じました。
手に土の温もりを感じるとともに、サラサラ感やザラザラ感が伝わってきました。
ふと、小学生の時に「土に触れた」体の感覚が蘇ってきました。
今回「土に触れた」感覚から、子どもの頃に「土に触れた」感覚が呼び覚まされるのを感じました。
発達心理学の知見によれば、吾々人間の体は、特に子どもの頃の体の感覚をよく覚えているとのこと。

収穫した芋のように、土が付いたままの芋は、日頃、スーパーやコンビニ等で見かけることはまずありません。
土の付いた芋を見ていると、とても新鮮な気持ちになり、「これが自然の姿なんだ!」と感じました。
「自然体験」と言うと大げさですが、「芋掘り」をして清々しい気持ちになりました。
この群馬旅行で久しぶりに「ある体験」をしました。
それは「芋掘り」です。
「芋掘り」と言えば、小学生の時に学校の農園で行って以来、ウン十年ぶりです。
考えてみれば、最近、私自身、日常生活の中で「土に触れる」ことがほとんどありません。
土などの自然由来のものに触れる機会を、日常的に失ってしまっているのが、都会に住む吾々現代人の生活なんだと感じます。
「芋掘り」で味わった、土の感触は何とも言えません。
土の中に手を突っ込んで、芋を掘り起こしているときに、腕から先の肌の感覚が鋭敏になり、活性化するのを感じました。
手に土の温もりを感じるとともに、サラサラ感やザラザラ感が伝わってきました。
ふと、小学生の時に「土に触れた」体の感覚が蘇ってきました。
今回「土に触れた」感覚から、子どもの頃に「土に触れた」感覚が呼び覚まされるのを感じました。
発達心理学の知見によれば、吾々人間の体は、特に子どもの頃の体の感覚をよく覚えているとのこと。
収穫した芋のように、土が付いたままの芋は、日頃、スーパーやコンビニ等で見かけることはまずありません。
土の付いた芋を見ていると、とても新鮮な気持ちになり、「これが自然の姿なんだ!」と感じました。
「自然体験」と言うと大げさですが、「芋掘り」をして清々しい気持ちになりました。
先日、私が山手線に乗っていた時のことです。
私は多少込んでいる電車の中で、つり革につかまったまま、いつも通り、本を読んでいました。
私の斜め前の席に座っていた年配の男性が、年配の女性に席を譲っている姿が、ふと目に入ってきました。
男性は、女性が自分より年上だから席を譲ったのか、「レディファースト」で席を譲ったのかは分かりませんでしたが、“紳士の振る舞い”に、私は感激しました。
私は多少込んでいる電車の中で、つり革につかまったまま、いつも通り、本を読んでいました。
私の斜め前の席に座っていた年配の男性が、年配の女性に席を譲っている姿が、ふと目に入ってきました。
男性は、女性が自分より年上だから席を譲ったのか、「レディファースト」で席を譲ったのかは分かりませんでしたが、“紳士の振る舞い”に、私は感激しました。
すると、その男性の隣の席に座っていた20歳前後の女の子が席を立って、「こちらにお座りください」と、年配男性に席を譲ったのです。
私は「最近の若者も捨てたものじゃないな!」と思いました。
ところが、その年配男性は女の子が譲ってくれた席に座ろうとしませんでした。
私は「最近の若者も捨てたものじゃないな!」と思いました。
ところが、その年配男性は女の子が譲ってくれた席に座ろうとしませんでした。
私は内心「この男性も、女の子の折角の厚意に応えてあげてもいいのに・・・。この子はきっと勇気を出して席を譲ったんだろうに・・・」と思いました。
誰も座らない、ポツリと空いた席が一つ・・・。
私は「この子の厚意を無駄にするのもかわいそうだし、(考え過ぎかもしれませんが)今回の“経験”に懲りて、この子が席を譲らない人になっても困るしな・・・」と(余計なお節介ですが)思いました。
ふと、私の右隣に年配男性が立っていることに気づきました。
「こちら、空いていますから、.どうぞ!」と、私はその男性に席を勧めました。
誰も座らない、ポツリと空いた席が一つ・・・。
私は「この子の厚意を無駄にするのもかわいそうだし、(考え過ぎかもしれませんが)今回の“経験”に懲りて、この子が席を譲らない人になっても困るしな・・・」と(余計なお節介ですが)思いました。
ふと、私の右隣に年配男性が立っていることに気づきました。
「こちら、空いていますから、.どうぞ!」と、私はその男性に席を勧めました。
この年配男性は、吾々の気持ちを「察知」してくれたのか、席に座ってくださいました。
この話から私が言いたいことは、私の行為は、20歳くらいの女の子の「勇気ある行為」があったからこそ、行えたんだということです。
また、席を立つという女の子の行為も、年配男性が年配女性に席を譲るという行為があったからこそ、行われたんだと思います。
私自身、人の「善意からの行為」は周りに伝わるということを、改めて体験しました。
総裁・谷口雅宣先生は、最新刊『“森の中”へ行く』の「はしがき」で、次のようにお説きくださっています。
<< ・・・(前略)・・・満員電車で老人に席を譲るような“正しい行い”は、それ自体が偉大な力をもっている。
本当は自分でやりたくても、いろいろな理由をつけて実行しない行為を、目の前で他人がした時、自分の中の“本心”に多くの人が目覚めるに違いない。・・・(後略)・・・ >>
(同書5~6頁)
誰もが他人の“正しい行い”に接したときに、「この人は素晴らしいな!」と感じたり、「自分も見習いたいな!」と思ったりした経験はあると思います。
自分自身で“正しい(と考える)行い”をしたときに、自己の“本心”が喜ぶ瞬間を、誰もが味わったことがあると思います。
先ほどの電車内は、何とも言えない“ほのぼのとした”雰囲気になりました。
※この記事は、私のツイッターの「4つのツイート」を元に、お幅に加筆して作成しました。
この話から私が言いたいことは、私の行為は、20歳くらいの女の子の「勇気ある行為」があったからこそ、行えたんだということです。
また、席を立つという女の子の行為も、年配男性が年配女性に席を譲るという行為があったからこそ、行われたんだと思います。
私自身、人の「善意からの行為」は周りに伝わるということを、改めて体験しました。
総裁・谷口雅宣先生は、最新刊『“森の中”へ行く』の「はしがき」で、次のようにお説きくださっています。
<< ・・・(前略)・・・満員電車で老人に席を譲るような“正しい行い”は、それ自体が偉大な力をもっている。
本当は自分でやりたくても、いろいろな理由をつけて実行しない行為を、目の前で他人がした時、自分の中の“本心”に多くの人が目覚めるに違いない。・・・(後略)・・・ >>
(同書5~6頁)
誰もが他人の“正しい行い”に接したときに、「この人は素晴らしいな!」と感じたり、「自分も見習いたいな!」と思ったりした経験はあると思います。
自分自身で“正しい(と考える)行い”をしたときに、自己の“本心”が喜ぶ瞬間を、誰もが味わったことがあると思います。
先ほどの電車内は、何とも言えない“ほのぼのとした”雰囲気になりました。
※この記事は、私のツイッターの「4つのツイート」を元に、お幅に加筆して作成しました。
数年前に、ある教区の春季中学生練成会(中学生を対象にした、生長の家の合宿形式のつどい)に出講しました。
参加した中学生たちはみな素晴らしく輝いており、練成会を受講する姿は真剣そのものでした。
座談会の時間には、「今回、青少年練成会に参加したみんなで、ジュニア友の会(生長の家の中学生のあつまり)を発会しよう!」とか、「毎月、ジュニア友の会を開いて、みんなでまた集まろう!」とか、いろいろと決意してくれるなど、非常に頼もしさを感じました。
「この子たちが、将来の生長の家を担ってくれるんだ!」
そう思うと、嬉しくなりました。
ただ一つ気になったことがありました。
それは、食事の時における、ある中学生の姿勢でした。
テーブルの上で、うずくまっているような姿勢で食べています。
さすがにあまりにもひどかったので、「これはほっとく訳にはいかない!」と思いました。
でも、こんな時には、注意の仕方に本当に気を遣います。
「何と言ったらよいか?」と考えました。
「そうだ、“日時計主義”の言い方で言おう!」と思いました。
“日時計主義”とは、「人生の明るい面、人の良い面を観る生き方」のことです。
「でも、こういうときに、どういう言い方が“日時計主義”なんだ・・・」と一瞬、考えました。
「心の中で、その子の完全円満なる実相(本当の姿)を祈りながら、とにかく、相手の中に“悪”なるものを観ない、指摘しない言い方ならいいんじゃないか!」と思い、次の台詞にしました。
「正しい姿勢で食べると、もっと美味しくなるよ」
その中学生は一瞬、キョトンとしていましたが、こちらが意図することを直ぐに理解し、姿勢を正してくれました。
以後の食事の時間に、その中学生を意識し観察していましたが、いつも、背筋をしっかりと伸ばして食べていました。
「やはり“日時計主義”の生き方は素晴らしい!」ということを実感しました。
参加した中学生たちはみな素晴らしく輝いており、練成会を受講する姿は真剣そのものでした。
座談会の時間には、「今回、青少年練成会に参加したみんなで、ジュニア友の会(生長の家の中学生のあつまり)を発会しよう!」とか、「毎月、ジュニア友の会を開いて、みんなでまた集まろう!」とか、いろいろと決意してくれるなど、非常に頼もしさを感じました。
「この子たちが、将来の生長の家を担ってくれるんだ!」
そう思うと、嬉しくなりました。
ただ一つ気になったことがありました。
それは、食事の時における、ある中学生の姿勢でした。
テーブルの上で、うずくまっているような姿勢で食べています。
さすがにあまりにもひどかったので、「これはほっとく訳にはいかない!」と思いました。
でも、こんな時には、注意の仕方に本当に気を遣います。
「何と言ったらよいか?」と考えました。
「そうだ、“日時計主義”の言い方で言おう!」と思いました。
“日時計主義”とは、「人生の明るい面、人の良い面を観る生き方」のことです。
「でも、こういうときに、どういう言い方が“日時計主義”なんだ・・・」と一瞬、考えました。
「心の中で、その子の完全円満なる実相(本当の姿)を祈りながら、とにかく、相手の中に“悪”なるものを観ない、指摘しない言い方ならいいんじゃないか!」と思い、次の台詞にしました。
「正しい姿勢で食べると、もっと美味しくなるよ」
その中学生は一瞬、キョトンとしていましたが、こちらが意図することを直ぐに理解し、姿勢を正してくれました。
以後の食事の時間に、その中学生を意識し観察していましたが、いつも、背筋をしっかりと伸ばして食べていました。
「やはり“日時計主義”の生き方は素晴らしい!」ということを実感しました。
ツイッター
カレンダー
ブログ内検索
最新記事
(09/25)
(12/09)
(03/15)
(03/03)
(02/15)
(02/09)
(02/05)
アーカイブ
最新コメント
[10/20 辻井映貴]
[03/15 てんこ]
[03/02 酒井幸江]
[02/10 高橋 久代]
[02/10 大段 務]
最新トラックバック
カウンター
カテゴリー
プロフィール
HN:
近藤 慎介 (こんどう のりゆき)
HP:
性別:
男性
職業:
宗教法人「生長の家」本部職員
趣味:
自分を高めること、読書、サッカー、柔道、英語、認知科学など
自己紹介:
滋賀県出身
東京都在住
千年以上続く、真言宗(高野山真言宗)の寺院(岡山県)の家系に生まれる。
真言宗の僧侶である祖父(権大僧正)と伯父(大僧正)を持つ(ともに大阿闍梨)。
昭和前期に、父方の祖母と母方の祖父が生長の家に触れる。
母より生長の家のみ教えを伝えられ、青少年練成会(小中高生向けの合宿形式のつどい)に参加する。
大学卒業後、民間会社に勤務の後、平成18年5月に宗教法人「生長の家」本部に奉職する。
平成22年3月、本部講師を拝命、現在に至る。
平成22年7月、生長の家教修会(生長の家の学会)で、「今日の自然観(心理学の視点から)」についての発表担当を務める。
<マイツイッター>(ブログ形式)
http://twilog.org/Shingon_Sni
<人生の7つの目標>
1.自分の使命と役割を全うする
2.人間の差別を克服する
3.人類の飢餓を克服する
4.宗教・宗派間の融和を実現する
5.自然と人間との大調和を実現する
6.世界の永久平和を実現する
7.地上極楽浄土を実現する
東京都在住
千年以上続く、真言宗(高野山真言宗)の寺院(岡山県)の家系に生まれる。
真言宗の僧侶である祖父(権大僧正)と伯父(大僧正)を持つ(ともに大阿闍梨)。
昭和前期に、父方の祖母と母方の祖父が生長の家に触れる。
母より生長の家のみ教えを伝えられ、青少年練成会(小中高生向けの合宿形式のつどい)に参加する。
大学卒業後、民間会社に勤務の後、平成18年5月に宗教法人「生長の家」本部に奉職する。
平成22年3月、本部講師を拝命、現在に至る。
平成22年7月、生長の家教修会(生長の家の学会)で、「今日の自然観(心理学の視点から)」についての発表担当を務める。
<マイツイッター>(ブログ形式)
http://twilog.org/Shingon_Sni
<人生の7つの目標>
1.自分の使命と役割を全うする
2.人間の差別を克服する
3.人類の飢餓を克服する
4.宗教・宗派間の融和を実現する
5.自然と人間との大調和を実現する
6.世界の永久平和を実現する
7.地上極楽浄土を実現する