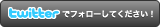[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
先日、私の住むマンションに向かって歩いていた時のことです。
前方に、お母さんと娘さんと思われる、非常に仲の良さそうな“二人組”が歩いているのを発見しました。
何と、二人は腕まで組んでいます。
お母さんと娘さんの仲の良さが、こちらにも伝わってきます。
「最近、“あのような”母娘をよく見かけるけど、あれが“友だち親子(母娘)”ってやつなんだな!」と思いながら、私はそのまま歩いていました。
あまりに仲の良い二人を見ていると、私も嬉しく楽しい気持ちになります。
自然と笑みがこぼれてきました。
「母親にとって、娘は、息子とはまた違った存在なんだろうな!」
「母親にとって、娘は、まさに“自分の分身”なんだろうな!」
「母親はきっと、娘の姿に、若かりし頃の自分をダブらせながら、見ているんだろうな!」
などと考えながら、私は歩いていました。
「そう言えば、僕の母も、妹と“あのように”していたのを見たことあるよな!」と、故郷に住む母と、数年前に嫁いだ妹のことを思い浮かべました。
「この前、母と妹が仲良く料理をしている姿を撮した写真が、妹から届いたっけ!」と、妹が送ってくれた写メールのことを思い出しました。
いつの間にか、目の前の“二人組”に、自分の母と妹の姿を重ね合わせていました。
前方を歩く、仲の良い“二人組”の親子も、相変わらず寄り添って歩いています。
「あの母娘の家庭は、きっと円満大調和なんだろうな!」
「明るく、笑い声の絶えない家庭なんだろうな!」
「母親にとって、娘と楽しくいられる時間って、本当に幸せで、至福の瞬間なんだろうな!」
などと考えながら、私は“二人組”の後ろを、一定の距離を保ちつつ歩いていました。
しばらく歩いていて、私は「えっ!!」とビックリしてしまいました。
何と、その親子は腕を組んだまま、私の住んでいるマンションの入り口の方に曲がっていったのです。
「あんな仲睦まじい母娘って、誰だ?!」と一瞬思いましたが、すぐに分かりました。
私の住んでいるマンションの大家さん親子だったのです。
娘さんを見かけることはほとんどありませんが、大家さんはいつも夫婦ご一緒で、非常に仲が良く、笑顔が絶えない、ハキハキとした明るい方です。
「あの明るさの秘密は、娘さんも含めた、家庭の円満さにあったんだ!」と思いました。
「“本当の幸せ”って、実は身近なところにあるんだな!」と感じました。
これらは、発電中のCO2発生量が“限りなくゼロ”(ゼロ)であるとともに、地球という惑星が存在するかぎり、エネルギーを使い切ってしまうという心配がありません。
また、原子力発電で出てしまうような、放射性廃棄物の発生などの問題も、ほとんどありません。
さらに、一次エネルギーの自給率が約4%しかなく、残りを輸入に頼っている日本にとって、“国内で生産”できる自然エネルギーは、資源をめぐる国際間の紛争の解消という面からも、まさに“救世主”と言えるものです。
その他、エネルギーの無駄を“ゼロ”にするための社会構築のプラン、省エネ構造の家屋、電気自動車など、現時点ですでに実用化の段階に入りつつある技術が多数あるのです。
さらに、今後、人類が“智慧”を結集し、“発明”するものを含めれば、吾々の目の前には、地球温暖化の解決に向け、技術的な方面からアプローチする方策等が、実は“無限”にあると言えるのではないでしょうか?
産業革命以降、人類は快適で豊かな生活を送ることを飽くなきまでに追求し、大量生産、大量消費、大量廃棄というライフスタイルのもと、石油を中心とする化石燃料を湯水のように使って生活し、大量の二酸化炭素を出しながら、経済発展を遂げてきました。
しかし、現代に生きる吾々がこれまで通りの生き方をしていたのでは、吾々の子どもや孫以降の世代が生きる時代には、いよいよ気候変動が激しくなり、人々の犠牲も増加し、経済も悲惨な状態になってしまいます。
総裁・谷口雅宣先生は、『小閑雑感』パート12の「はじめに」で、次のようにお説きくださっています。
「(リーマン・ショックに始まる世界金融不況に関して) 経済は人間心理の産物であるから、行きすぎた“ブーム”は、ある時点で“バブル崩壊”によって修正される。
これは、人間の心が間違いに気づくことだから、善いことである。
が、次にくる“反省”の局面で、人類が正しい選択をすることが決定的に重要である。
そうでなく、従来のように自然や地球環境を犠牲にした経済発展や、欲望優先のマネーゲームを続けていても、「案外いけるかもしれない」などと発想を逆戻りさせる政策の実行は、人類全体にとって致命的になる。・・・<中略>・・・
指導者は今、消費者の選択のために“正しい方向”を明確に指し示す必要がある。
その方向とは、自然や地球環境を考えた低炭素社会実現のための各種技術や制度を育成する方向以外にない」
(同書「はじめに」より)
吾々人類が、これまでの資源浪費型の社会システムや経済システム、産業システムからの転換を、いつ決断し、実行に移すのかという段階に、すでに来ていると言えるのではないでしょうか?
吾々人類が、これまでの資源浪費型の個々人間の生活スタイル(生活習慣)からの転換を、いつ決断し、実行に移すのかという段階に、すでに来ていると言えるのではないでしょうか?
そして、人類が、これまでの人間至上主義にもとづく、社会のあり方と生き方から転換し、「自然と共に成長できる社会」、つまり“低炭素社会” “資源循環型社会”を実現し、“自然エネルギー社会”を構築していくことこそが、吾々人類には求められていると言えるのではないでしょうか?
人類には、今まさに“文明の転換期”が訪れているのだと感じます。
「ニュートン」2010年4月号によると、2007年度、日本の国別の全体排出量は、中国、アメリカ、ロシア、インドに次いで、5番目とのこと。
また、国民一人あたりの排出量は、アメリカ、オーストラリア、カナダ、ロシア、韓国に次いで、6番目とのこと。
(いずれも化石燃料の燃焼にともなう排出のみ)
それだけ、日本(日本人)は、地球環境問題に対する責任が大きいということであるとともに、解決のためにも大いに貢献していけるということです。
今こそ、吾々一人ひとりが、その心により現象世界を形作っていく“主体者”としての神の子の自覚を持って、“未来世代の幸福”のために立ち上がりましょう!!
「ニュートン」2010年4月号(ニュートンプレス発行)で、「温暖化を知るためのCO2」についての特集が組まれ、「(CO2の)地球温暖化への影響や削減方法など、いま必要とされている情報をわかりやすく紹介」(16頁)しています。
「現代の科学者は、CO2がふえることでおきるのは気温の上昇にとどまらず、地域によっては気候変動や水や食糧の不足などもおきると予測している。
海水の酸性化もCO2の増加が原因でおきるといわれている。
しかもこれらは1000年先ではなく、数十年先におきる可能性があるという」
(同書18頁)
※「海水の酸性化」により、サンゴの白化や植物プランクトン(海の食物連鎖の“土台”である)の成長阻害等が起こり、海の生態系や地球の気候に影響を及ぼすとされている。
地球温暖化の原因とされる、温室効果ガスの一つ「CO2(二酸化炭素)」。
人類が、その活動により、大量のCO2を排出しているために、大気中のCO2濃度が、ここ200年間で著しく高くなり、気温の上昇を引き起こしていると言われています。
このまま地球環境問題が深刻化し、地球温暖化が“臨界点”を超えてしまえば、今世紀末には世界の気候に大変動が起こり、人類の生存そのものも危うくなる恐れがあると予測されています。
そのため、CO2の排出量の削減が、世界的な課題となっているのです。
同書では、CO2の観点から「地球温暖化」や「海水の酸性化」などについて、また、自然界での「炭素循環」やCO2の「海洋への閉じこめ」(海水によるものと生物によるものとがある。CO2の「地中貯留」とは別のことです)、地球の「温室効果」の仕組み、森林による「光合成」など、自然界の“神秘”(メカニズム)について、イラスト等を交えながら、分かりやすく解説しています。
また、CO2の国別の排出量と削減目標、日本における発生源別のCO2排出量の内訳や世帯でのCO2排出量の内訳等が、グラフ等を交え、視覚的に分かりやすく書かれています。
さらに、同書には、吾々の日常生活(家庭部門、交通部門等)や産業部門、業務部門、運輸部門などでの、CO2削減のための、様々な先駆的な科学技術(アイデア、プラン)が紹介されており、非常に“前向きな気持ち”にさせてくれます。
例えば、省エネ構造の家屋や、自然エネルギー、電気自動車などについて、CO2排出量やエネルギー効率の観点から、これまでのものとの比較をしながら、分かりやすく紹介しています。
私が「なるほど!」と思ったのは、「エネルギーの融通」により、エネルギーの無駄をなくす社会を構築するというプランです。
これにより、究極的にはエネルギー(熱エネルギー、電気エネルギー、化学エネルギーなど)を捨てる量を“ゼロ”にすることが可能になるそうです。
「空間」を超えた「エネルギーの融通」としては、工場間同士で行うものや、工場とオフィス、家庭、自動車との間で行うものなどが考えられているそうです。
また、「時間」を超えた「エネルギーの融通」としては、夏と冬などの季節間のものが考えられているそうです。
同書を読めば、地球温暖化問題という全人類の課題に、様々な方面から取り組もうとする、人類の“叡智”に、大いなる希望を感じることでしょう!
合わせて、お楽しみください。
素晴らしいコメントも、いくつかいただきました。
現在、ポスティングジョイと私のブログとを結びつける、ネットの活用について“試行錯誤”しています。
クリーニング屋では、いつも通りの手続きを経て、会計を済ませました。
最後に、店員さんから「仕上がりは月曜日になります」と言われました。
私は、心の中で、「えっ、今日は木曜日だよな? いつも、そんなに時間、かかったっけ!?」と思いました。
クリーニングを出す時間帯にもよりますが、通常は、昼前に出せば、翌日か翌々日の夕方には仕上がります。
別に急いでいるわけではありませんでしたし、私の性格上の問題もあり、特に店員さんに「何でそんなに時間がかかるの?・・・」などと、“確認”はしませんでした。
「月末か何かの関係とか、曜日の“巡り合わせ”の関係か何かで、今回はたまたま時間がかかるのかな?」とか、「クリーニング屋で、何かシステムが変わったのかな? “外部委託”になったとか・・・」などと、帰りがけに少し考えました。
ただ、「この時代に、クリーニングの仕上がりに、そんなに日数がかかって、店として大丈夫かな?」と、内心は思いました。
しかし、考えてみれば、私は、これまで、仕上がり日にクリーニングを取りに行っているわけではなく、店の営業時間(8:00~20:00)と私の通勤時刻の関係もあり、だいたい一週間から十日遅れで取りに行っていることに気づきました。
「私のように、なかなか受け取りに来ない客が“多い”から、あの店の店内は、“受け取り待ち中”のクリーニングで、いつも溢れているわけだし・・・。仕上がりが早い遅い何か、別にどうでもいいか・・・」と思いました。
そもそも、スーツを何着か持っているため、「その一着」が翌日か翌々日に返ってこなければ、着るものがなくて困るというわけでもありません。
また、クリーニングを受け取りに行った翌日に、「その一着」を早速着て、仕事に行っているわけでもありません。
スーツの“ローテーション”を少し変えれば良いだけです。
「はっ!」としました。
いつの間にかサービスに「速さ」を求めてしまっている自分に、気づいたのです。
さらに、その「速さ」を“当たり前”のことと思ってしまっている自分に・・・。
ただ、この「記事」を一通り書き終わって、クリーニングの「お預り票」を、念のために確認しました。
「・・・」
実は、「お預り票」には、「明日金曜日の18時以降の仕上がり」と印字されていたのです。
初めから、“いつも通り”の仕上がりだったのです。
私が店員さんの言葉を聞き間違えたのか、店員さんが外国出身の方だから言い間違えたのか・・・。
確かにサービス等に「速さ」が必要なときもあります。
しかし、吾々現代人は、とかく、日常生活の中で、たいして必要でもないのに、サービス等に「速さ」を過剰に求めてしまってはいないでしょうか?
いつの間にか、特段必要でもないのに、「速いこと」を“当たり前”のことと感じてしまっていることはないでしょうか?
そして、人生にも・・・、食事(食料)にも・・・。
今回のクリーニング屋での出来事を通して、色々と考えさせられました。
オリンピックのモーグルの予選が、テレビ中継されていました。
前回、紹介した“彼女”が登場する前の時間帯でのことです。
地元・カナダ出身の「彼女」は順調に滑り始めました。
しかし、「エア」を飛んだ後、バランスを崩して、豪快に転倒し、前のめりに倒れ込んでしまったのです。
しかも、転倒する途中で、スキー板が外れてしまいました。、
「これまで何年にもわたり、必死に努力してきたのに、せっかくのオリンピックの舞台で、このような形で“終わって”しまい、さぞかし悔しいだろうな」と、私はその姿を、悲痛な思いで観ていました。
テレビ解説者が言うには、10秒以内に競技を「再開」しなければ、「失格」になってしまうとのこと。
「今さら競技に戻っても、完全にアウトじゃないか! しかも、スキー板が外れてしまっているわけだし!」と、私は思いました。
しかし、「彼女」は倒れたままの状態から、腕を使い、体を滑らせながら、急な斜面を昇っていこうとしたのです。
ルールのせいで、競技場の「雪上」で立ち上がってはいけないからでしょうか?
数メートル上のスキー板があるところまで、仰向けのまま、頭部を下側に向け、両腕を使って、必死に急な勾配を登ろうとする「彼女」。痛々しささえ伝わってきました
私は、息をのんで、画面を観ていました。
何とかスキー板があるところまで戻り、スキー板を急いで着用する「彼女」。
次第に、会場から、大きな歓声と拍手が聞こえてきました。
「彼女」が地元・カナダ出身ということもあると思いますが、おそらく、予選では一番、大きな歓声と拍手が起こった瞬間ではなかったかと思います。
「彼女」は、何とか競技を「再開」することができました。
観客からの声援と拍手が、ますます大きくなってきました。
「再開」後の「彼女」の滑りは、素人の私から見ても、見事なものでした。
「彼女」は最後まで、しっかりと滑り切りました。
テレビに映る、競技を終えた「彼女」の表情は呆然といった感じでしたが、会場からは、「優勝」が決まったかのような歓声と盛大な拍手が沸き起こってきました。
非常に感動的でした。
最終的に、「彼女」の結果がどうなったかは分かりません。
もしかすると、競技を「再開」した時点で「10秒」を超えていて、すでに「失格」だったのかも知れません。
「失格」は免れていても、おそらく「予選落ち」になってしまったと思います。
でも、「彼女」が競技を「再開」し、必死にプレーを続ける姿、そして観客が盛大な歓声と拍手を送るシーンを観ていて、本当に重要なものは何なのかを考えさせられました。
競技の「勝ち負け」や「メダルの有無」、「決勝進出云々」ということが全てではない、「その時その時に、自分ができることを、必死になって、いかに心を込めてやり切るかの方が、もっと大切だ!」ということを、教えていただいたように感じました。
観客も、諦めずにプレーを続け、しっかりと最後まで滑り切った「彼女」の姿に、“自然と”歓声と拍手が出てきたのだと思います。
生長の家創始者・谷口雅春先生は、『新版 希望を叶える365章』で、次のようにお説きくださっています。
「何事がやって来ても、心を動揺させてはならない。
結局、悪しきものは存在しないし、悪しきものは我らを襲い来ることはあり得ないからである。
私たちの人生の行路は必ずしも平坦ではない。
しかし、平坦でないから足が鍛えられて健脚となるのである。
困難と見えるものは自己に内在する“無限力”を一層多く汲み上げるところのポンプ作用である。
・・・<中略>・・・人生の経験に無駄はひとつもないのである。
困難に挑戦することによって、“内在の力”は一層多く発揮せられることになり、自分の魂の能力のうち、まだ完全にみがかれていない部分を琢磨して輝かすことになるのである」
(同書146頁より)
「彼女」の年齢は、まだ17歳だとのこと。
今回の「経験」を糧に、一層飛躍した「彼女」が、次回のオリンピックで見られそうです。
「オリンピックで全力で滑ることができて満足です。ちょっと悔しいけど」
「オリンピックでメダルは取れなかったけど、自分の持てる力を出し切れたと思います」
「いい滑りをしたというところを、みんなに見てもらえたと思う」
オリンピックのモーグルで競技を終えた、“彼女”の台詞です。
やはり一つのことに、本当に全力で、本気で、とことんまで取り組んできた“彼女”だからこそ、出てくる台詞です。
マスコミは、「またも悲願のメダルに届かず」 「4位に終わる」 「メダルまで一歩届かず」・・・何てコメントしています。
正直なところ、僕には「結果がどうこう・・・」という気持ちは、全く起こってきません。
そもそも、4大会連続でオリンピックに出場したり、ましてや順位を一つずつ上げながら、4大会連続で入賞を果たすことは、とてつもなく凄いことだと思います。
何よりも、「とことんまで全力を出し切った姿」が感動的でした。
競技が終わってからもしばらくは、“魂からの感動”で胸がいっぱいになりました。
生長の家創始者・谷口雅春先生は、『新版 希望を叶える365章』で、次のようにお説きくださっています。
「一着になるとか、何分何秒とかいう“秒読み”にも似た財産増加の速度などは大して重要な事柄ではないのである。
その目標に到達するための精神の練り方が問題であるのである。
神は或る目標を吾らの前に置いて、その魂の進歩の資料となし給うのである。
何事を為すにも「魂を練る」ための資料として為すことが大切である」
(同書79頁より)
結果が“彼女”よりも良かった選手が3人いたから、「4位入賞」だったかもしれませんが、全てを出し切った“彼女”は、最高に輝いていました! 悔いがあるはずはありません!
“彼女”がバンクーバー・オリンピック直前に著した書籍、『やさしく、強く、そして正直に』(上村愛子著、2010年2月刊)の「エピローグ」の一部をご紹介します。
「わたしの今度のオリンピックでのすべりは、今まで自分に時間をつくってくれたすべての人たちへの恩返しとしてすべりたいと思います。
皆さんに、「ありがとう」が言えるすべりを必ずしたい。
常にコブに対してチャレンジ精神をもって向かっていきたい。
相変わらず誰かに勝ちたいとは思わないけれど、コースには絶対に負けたくない。
そこを皆さんに見てもらえたらいいなと思っています」
(同書152頁)
本当に“最高の滑り”でした。
これは、「人間が自然の仲間入りをさせてもらい、森の機能を活かしたまま業務を遂行し、自然と人間が共存共栄する社会を目指す“自然と共に伸びる運動”の一層の伸展を目指」(生長の家ホームページ 【ニュースリリース】 「自然と人が共生する国際本部建設へ」より)すものです。
“森の中のオフィス”の建設予定地の近くには、俳優の柳生博(やぎゅうひろし)氏が整備された、自然の雑木林の良さを体験できる「八ヶ岳倶楽部」など、森と人との調和を意図した様々な施設があります。
最近、柳生博氏のご著書「八ヶ岳倶楽部Ⅱ それからの森」(講談社、2009年8月刊)を読みました。
ここで、「柳生氏流のエコロジー」についてご紹介します。
柳生氏は、30数年前、世の中に「エコ」という言葉がなかった時代に、八ヶ岳南麓の地に、家族とともに「移住」されました。
そして、近隣の人工林からもらい受けた多様な広葉樹を、敷地内に移植し、見事な雑木林を造り上げられたのです。
柳生氏は、現在、芸能活動や講演活動の傍ら、八ヶ岳でギャラリー&レストラン「八ヶ岳倶楽部」の経営と「作庭」をされています。
2004年からは、日本野鳥の会の会長を務め、会の活動にも勤しまれています。
上掲書の中から、少しご紹介いたします。
「里山の中で自然と折り合いをつけながら、季節の移ろいを感じながら、田んぼや畑、そして森の中にいる生き物たちをよく見て関係性を知る。
そうすると自分たち人間も、大いなる自然の中のごく一部だということに気づくはずです。
そんな謙虚さや、慎ましやかな誇り高さはとても大事なことだと思います」
(同書108頁)
「何もしないでは得ることができない確かな価値がそこにある。
懐かしい風景ってそういうものだと思うのです。
確かな未来は、人間が“生き物”としての感覚を取り戻した先にあるのです。
そう、そろそろ人間以外の生き物たちのことも考えましょうよ」
(同書158頁)
同書に掲載されている、自然と触れられる柳生氏やスタッフたちの姿を見ると、非常に生き生きとされ、表情も清々しく、穏やかでした。
「これが“本来の場所”に帰った人間の姿なんだ!」と感じました。
柳生氏たちの森の中での「ありのままの生活」から、吾々人間が自然(森)と触れ合うことで、現代的な生活の中で失った、人間の“本来の姿”を取り戻すことができること、自然には、人間の「心のバランス」を取り戻すことができる“不思議な力”があることなどを、改めて学びました。
同書を読み進めると、自然界のいのちの鼓動や、森の中での生き物の息遣い、自然の移ろいなどが、目の前にありありと感じられ、映し出されてくるのを感じました。
あたかも、自分自身が自然(森)の中に実際にいるかと錯覚するほど、非常に高い「臨場感」を感じました。
時は流れ、「八ヶ岳倶楽部」を訪れる人は年間10万人を超えていると言います。
同書には、都会で生活していたときには、対人関係が苦手だった女性が、八ヶ岳に来て、人が変わったように表情が豊かで朗らかになり、人と接することが好きになったなど、自然と人間との関係を示唆する、感動的な話も載っています。
みなさんも、人間と自然との「折り合い(おりあい)」の仕方、そして、自然と人間が「折り合う」ことで得られる、人類の「豊かな未来図」を考えてみてはいかがでしょうか?
2006年3月に、第1回WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)で、日本代表を初代王者(世界一)に導いた、王貞治監督。
シリーズ途中での敗戦に屈することなく、チームが一丸となって戦い、決勝戦で、強敵キューバを破って世界一に輝きました。
普段、野球を観ない私ですが、WBCは、第一ラウンド、第二ラウンド、決勝ラウンドと、手に汗を握りながら、テレビで日本代表を応援していました。
日本人の多くが勝利に歓声を上げ、敗戦に肩を落としていたことだと思います。
私は、年齢的に、王監督の選手時代をほとんど覚えていませんが、小学生の頃に、少年向けの雑誌に連載されていた『巨人の星』?(『巨人君』?)という漫画を読んでいたことがあり、王監督は非常に好きな選手(監督)でした。
そんな王監督ですが、数年前に胃ガンで入院されたことがありました。
王監督は、胃ガンの手術が成功し、無事退院されたときに、次のように話されていました。
「また、チームに戻って、優勝する喜び、負ける悔しさを味わいたい!」
一見すると、何でもない台詞ですが、非常に深い言葉だと感じました。
普通に考えると、「優勝する喜び」や「試合で勝つ喜び」を味わいたいということは、もちろん分かりますし、誰もがそう思います。
でも、王監督にとっては、「優勝する喜び」はもちろん、「負ける悔しさ」を味わうことも含めて、野球なんだということです。
愛する野球で、優勝しようが、試合に勝とうが負けようが、マスコミや観客に褒められようが貶されようが、「それが野球の楽しさだ!面白さだ!」 「味わい深いものなんだ!」 ということです。
王監督は、本当に心底、野球を愛していらっしゃるんだなと感じました。
王監督の台詞から、吾々自身が、人生や毎日の生活、仕事、学校、生長の家の信仰や活動、何らかの目標に取り組むこと等において、一見すると「喜び」と思えることや「悔しさ」と見えること、いずれにおいても、十分に「味わい楽しんで」いるだろうかと考えさせられました。
野球の日本代表に限りませんが、国を代表して試合等に出場される選手やチームの皆さんのことを、私は大変誇りに思うとともに、いつも大きな勇気をもらいます。
間もなく始まる「冬季オリンピック」でも、出場される選手の皆さんやチームが、今まで練習されてきた成果を、存分に発揮されることをお祈りいたします。
野村監督が好きな言葉の一つが、「財を残すは下、仕事を残すは中、人を残すを上とす」だそうです。
最後の監督指揮となった日本ハム戦の終了後には、楽天と日本ハムの両チームの選手やコーチに、野村監督が胴上げされるという感動的なシーンがありました。
その時のインタビューで、野村監督は、次のようなことを話されていました。
「日本ハムにも稲葉や坪井とか一緒にやった連中がいて、お別れをしてくれた。
感無量というか、胸が詰まった。
縁だよ。縁を持った人がユニホームを着て頑張っているのは、喜ばしいこと。
人間、何を残すか。人を残すのが一番。
少しくらいは野球界に貢献できたかなと。そういう心境です」
名将・野村監督の手腕により、「再生」した選手や「プロ入り」を果たした選手は数知れず、「野村再生工場」と呼ばれていたことは有名な話です。
「不遇」を囲っていた人材が、野村監督のもとで、その才能を開花させ、「人財」となって羽ばたいていきました。
改めて、人を育てるのも、人をダメにするのも、周囲の人間の力が大きいのだと感じました。
それにしても、特に監督として、あれだけの「実績」を残されながら、このような謙虚な発言をされるあたりが、素晴らしいと思います。
人はとかく、物質的な豊かさや収入、地位、名誉、学歴、仕事や学校の成績等の「財」を求めがちですが、野村監督の言葉から、もっと大切なものは何かを考えさせられました。
さらに言えば、「財を残すは下、仕事を残すは中、人を残すを上とす」という言葉は、「人を残す」ことを、単に「財を残す」ことや「仕事を残す」ことと比較し、「人を残す」ことがより重要だと言っているわけではないと思います。
「財」(単に物質的な財産だけではなく、努力により蓄積してきたもの、精神的・魂的な面で磨いてきたものなど)の上に、「仕事」(社会や人の役に立つこと、人と人との協働作業、組織や団体などの人の集まりなど)があって初めて、「様々な人と人との縁」が積み重なり、「人財」が育ち、「人を残す」ことができるということが言いたいのではないかと、私は思いました。
人を育てる「場」や「機会」、人と人との「縁」というものが大切なんだと痛感します。
吾々が生長の家のみ教えに何らかの縁があって触れ、真理を日々研鑽できることは、自分が「人財となる」ことにつながるのだと思います。
さらに、生長の家のみ教えを友人や知人に伝えていけば、真理を知ることで、相手の神性が開顕することを通し、「人財を残す」こと(人材の発掘と育成)につながるのだと感じました。
このブログも、「人財を残す」ために、生長の家のみ教えとの「縁づくり」の一助となればと思います。
東京都在住
千年以上続く、真言宗(高野山真言宗)の寺院(岡山県)の家系に生まれる。
真言宗の僧侶である祖父(権大僧正)と伯父(大僧正)を持つ(ともに大阿闍梨)。
昭和前期に、父方の祖母と母方の祖父が生長の家に触れる。
母より生長の家のみ教えを伝えられ、青少年練成会(小中高生向けの合宿形式のつどい)に参加する。
大学卒業後、民間会社に勤務の後、平成18年5月に宗教法人「生長の家」本部に奉職する。
平成22年3月、本部講師を拝命、現在に至る。
平成22年7月、生長の家教修会(生長の家の学会)で、「今日の自然観(心理学の視点から)」についての発表担当を務める。
<マイツイッター>(ブログ形式)
http://twilog.org/Shingon_Sni
<人生の7つの目標>
1.自分の使命と役割を全うする
2.人間の差別を克服する
3.人類の飢餓を克服する
4.宗教・宗派間の融和を実現する
5.自然と人間との大調和を実現する
6.世界の永久平和を実現する
7.地上極楽浄土を実現する